合格の可能性を大幅上昇させる過去問の解き方
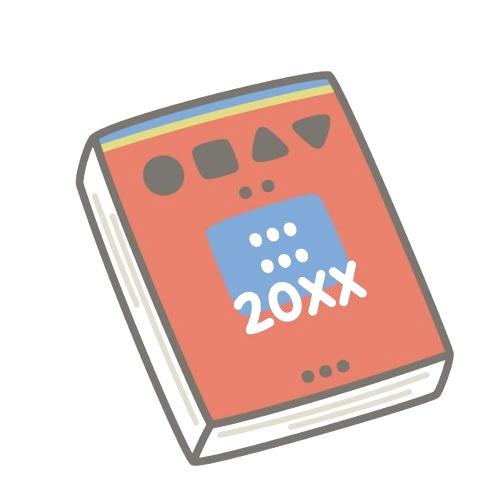
受験勉強で必ずと言っていいほど耳にするのが「過去問を解きなさい」という言葉です。 しかし実際のところ、多くの受験生が過去問を「ただ解いて点数を確認するだけ」で終わらせてしまっています。 これでは効果は半減どころか、むしろ自信をなくす原因になることさえあります。
過去問は、本番の練習として取り組むだけではありません。 出題傾向を知り、時間配分の戦略を立て、弱点を明確にして克服する──。 こうした使い方をしてこそ、合格可能性を大幅に引き上げることができます。
このページでは、家庭教師として数多くの受験生を合格へ導いてきた経験をもとに、 「過去問を解く目的」「やってはいけない使い方」「正しい活用ステップ」を詳しく解説します。
1. 過去問を解く目的
過去問を解くことには「実力を測る」以上の意味があります。正しい目的を理解することが、合格への第一歩です。
出題傾向をつかむ
学校ごとに問題の作り方には個性があります。 例えば、公立高校では基礎~標準問題を広く出題し、得点の安定性を重視する傾向があります。 一方、私立の難関校では短時間で高い思考力を求める問題が多くなります。 どんな問題が頻出なのかを知るだけで、勉強の優先順位が変わります。
時間配分や解く問題の選別をチェック
入試は試験時間が設定されており、毎年、問題の難易度や出題傾向は大きく変化することはありません。 そのため、本番と同じ状況で過去問を解くことで、時間配分や自分が解ける問題の選別を行うことができます。
改善が必要な教科と分野の確認
漠然と「数学が苦手」ではなく、「図形の証明で点が取れていない」「英語の長文で時間が足りない」と具体的に分かるのが過去問の強みです。 弱点を可視化することで、効率的に勉強できます。
合格者平均や合格最低点との距離を測る
現状の合格までの距離を測り、あと何点上げればいいのかを明確にできます。 それによって、入試までの学習計画を立てることができます。
学習の成果が点数化されモチベーションに繋がる
日々の学習は目に見える成果が出にくいため、「頑張っているのに実感がわかない」と感じることもあります。 過去問を解くことで、積み重ねた学習が点数となって表れ、「自分は確実に力をつけている」という手応えを得られます。 この成功体験が次の学習への大きなモチベーションとなり、受験勉強を継続するエネルギーになります。
2. 過去問を解く前にすべきこと
各教科の基本用語はすべて覚えておく
例えば、社会なら「資本主義」、理科なら「力学エネルギー」など。 用語の理解が曖昧だと、絶対に落とすことができない基本問題に正解できません。 それどころか、用語を知らないために、問題の意味が理解できないから解答しようがないということも起こりえます。
基礎となる1行問題・一問一答に取り組む
私立中学の難関校(大濠中、西南学院中など)であっても、まず重視されるのは「基礎を落とさないこと」です。 公立高校入試も同様で、基礎問題を確実に取れるかどうかが合否を大きく分けます。 ですから、過去問に進む前に、計算・用語・知識問題といった1行問題や一問一答形式の問題を繰り返し解き、定着させておく必要があります。
網羅系問題集を最低でも2回まわす
1回で「やったつもり」になるのは危険。2回目で定着し、初めて得点源になります。 過去問に進む前に「基礎~標準問題なら大半を落とさない」状態にしておくことが必須です。
3. よくある間違った解き方
過去問の効果が出ない生徒には共通点があります。
点数で一喜一憂する
「合格者平均点を超えた!やった!」と浮かれても、次の年度で大きく落とすことは珍しくありません。 たまたま得意な分野が出題されたから良かっただけかもしれません。
また、逆に悪い点数でも、落ち込む必要はありません。 合格最低点や合格者平均点は、過去の受験シーズンに受験した生徒の結果です。 入試までの1,2か月の期間があるのなら、まだまだ学力は伸びるはず。
特に中学入試の場合、過去問の結果が悪く、保護者が焦ってしまう場合が多いです。 「どうしてこんな点数なの!」と叱ると、子どもの自信は一気に崩れます。 どんな勝負事でも感情的になった時点で負けが決まってしまいます。
大切なのは「なぜその点数になったのか」を冷静に分析すること。過去問では感情は不要です。 ロボットになったつもりで、機械的に原因を抽出しましょう。
復習や分析をせずに次の年度を解く
1年分解いたら、徹底的に分析して復習することが最優先です。 よくやりがちなのは、結果が悪かったからといってすぐ次の年を解いてしまうことです。 その際、仮に良い結果が出たとしても、前の年で悪い結果が出たという事実を変えることができません。
良い結果と悪い結果の両方が出たとき、悪い結果のほうが生徒の実力を表しています。 たまたま良い結果が出ることはありますが、たまたま悪い結果が出るということはありません。 悪い結果のほうが生徒の真の実力です。
ですから、過去問を説いた後は、結果にかかわらず、徹底的に分析して復習することが重要なのです。
戦略を立てずに漠然と解く
本番で全問正解を目指す必要はありません。合格点に届けばいいのです。 取るべき問題と捨てる問題を決めずに解き始めると、難問に時間を浪費して失敗します。
限られた時間でどの問題に取り組むか、どの問題を潔く捨てるかが合否を分けます。 過去問を通して「試験が始まったら試験問題の後半にある漢字や慣用句の問題から解こう。」、 「第1問は8分、第2問は7分を目標に解こう。」など、戦略を立てることなく漠然と過去問を解いても意味がありません。
4. 合格を引き寄せる過去問の解き方
① 準備を整えてから挑む
網羅系教材を2回以上まわし、基礎・標準問題を安定して解ける状態にしてから過去問へ。
② 戦略を立てる
各教科の配点を確認し、「どの問題で得点を稼ぐか」「どの問題は捨てるか」を決める。時間配分も事前に考えておく。
③ 本番と同じ条件で解く
時間を計り、静かな環境で解く。本番に近い緊張感を持つことで「試験慣れ」する。
④ 厳しめの採点をする
自己採点は甘くなりがち。保護者が厳しく採点すると良いでしょう。
⑤ 戦略通りにできたか検証
予定通りの時間配分・問題選択ができたか確認。「計画を守れたか」を重視する。
⑥ 不正解の原因を分析
ケアレスミスか知識不足か、時間切れかを細かく分類する。ケアレスミスの場合は、同じミスを繰り返さないように対策を立てる。
⑦ 解き直しと復習
不正解の問題をその場で解き直す。さらにテキストや問題集で類題を練習し、弱点を補強する。
⑧ すぐ次に進まない
1年分終えたら必ず復習期間を設け、3日以上空けてから次の年度に挑戦する。 志望校が複数ある場合は、ほかの学校の過去問を解いても良いでしょう。
まとめ
過去問は「合格可能性を測るためのテスト」ではなく、「合格を引き寄せるための最強の教材」です。 ただ点数を確認するために解くのではなく、出題傾向を把握し、時間配分や戦略を磨き、弱点を補強するために使うことが大切です。
また、保護者のサポートも大きな力になります。 点数に対して感情的に反応するのではなく、 「どこを改善すれば次は伸びるのか」を一緒に考える姿勢が、子どものモチベーションを守り、最後まで努力を続ける原動力になります。
過去問は、やり方を誤れば「ただの点数チェック」で終わり、学力アップに繋がりません。 しかし、正しく取り組めば「合格への道しるべ」に変わります。 ぜひ、本ページで紹介した手順を意識しながら、過去問演習を合格への強力な武器にしてください。
なかなか成績が上がらずにお困りの方へ。 当サイトでは、実際の合格事例や勉強法のアドバイスも掲載しています。ぜひ他の記事もあわせてご覧ください。 また、無料学習相談もお受けしております。お気軽にご相談ください。
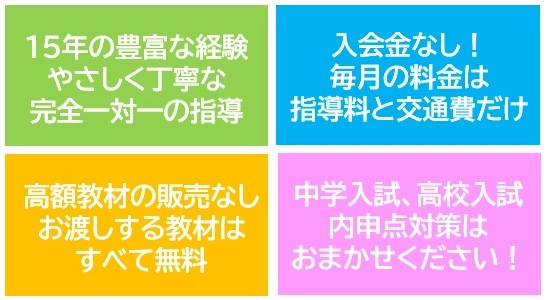
家庭教師ふなきちでは、継続的な指導だけでなく、単発指導にも対応しています。 さらに、単発指導をお得に受けられる4回セットプランもご用意しています。
4回セットプランは、1回の単発指導より10~25%OFFでお得に家庭教師の指導が受けられます。 詳細は料金案内ページをご覧ください。
